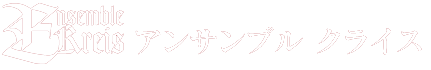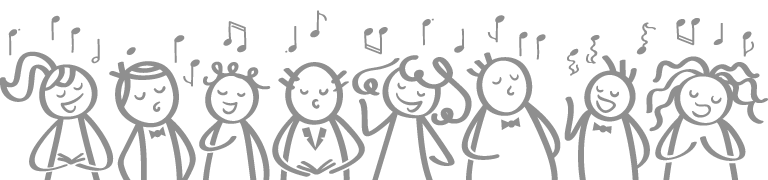
CONCERT
演奏会
アンサンブル・クライスの
演奏会活動記録です。
メンデルスゾーン《詩篇第115篇 Op. 31「私たちではなく、主よ」Der 115. Psalm op.31 'Non nobis Domine'》
聖書と詩篇
聖書はキリスト教の教典のことで、「旧約聖書」と「新約聖書」の二つの部分から出来ています。これは、ひとりの人が書いたのではなくて、何世紀にもわたって多くの人の手によって書かれた書物が編纂されて完成しました。
この「約」というのは、「契約」という意味で、創造主が人と結んだ契約ということです。「旧約」は、「旧(ふる)い契約」と言う意味で、「新約」が「新しい契約」という意味です。
◆旧約聖書とは
創造主が預言者に与えたメッセージを集めたもの。預言者とは創造主のメッセージを霊感で受けて預かる人たちのことで、「未来を予言する」の「予言」ではありません。
イエスが生まれる前のユダヤ人のことが書かれていて、もともとユダヤ教の教典でした。ですから旧約聖書はヘブル語(ヘブライ語)で書かれていました。しかし、のちに興ったキリスト教団が、「イエスについて預言したもの」だからということで、キリスト教の教典に収録しました。
旧約聖書の契約とは、律法(モーセの十戒を代表とする創造主の命令のこと)を守って生きれば、物質的な祝福を与えるという約束のこと。
◆新約聖書とは
イエスの伝記や、イエスの教えを伝道するために書かれた手紙などを集めて編集したもの。イエスの死後に弟子たちによって書かれました。こちらはギリシャ語で書かれています。
「新しい契約」が約束しているのは、イエスの言葉を心に受け入れれば、霊的・物質的両面での祝福が与えられるということです。
◆「詩篇」は旧約聖書の中の文書で、ユダヤ人によって収められた150篇の賛美、祈り、感謝、悔い改め、また神に対する信頼と愛情を表す詩によって構成されています。これらの美しい詩には、神に選ばれた民が、全知全能であられる創造主のもとでどのように成長し、学び、礼拝していたのかが巧みに描写されています。
詩篇が世界中で愛されている理由の一つは、その詩の言葉が神の言葉でありながら、限りなく人間の視点で表現されているという点にあるでしょう。
実際に詩篇を読んでみると、歌集というよりも、著者たちの信仰生活を綴った日記のようです。そこには神と共に歩む人が体験するさまざまな感情が、生々しく書かれています。喜びや感謝の心だけではなく、憤りや恐怖、後悔や失望した心によって執筆された詩篇も数多くあります。そして、さまざまな状況の中でどのようにして神に信頼し、畏れる心を持ち、主に希望を持つことができるのかが書かれているのです。

J.S.バッハ『イエスよ、わが喜び』
ヨハン・フランクの作詞によるコラール「イエスよ、わが喜び」(1650)の6つの節を核に、新約聖書『ローマの信徒への手紙』第8章からの章句を歌詞とした多声楽曲で注釈を加えるという構成をとる5声のモテットは、バッハがライプツィヒのトマス・カントルに着任して間もない1723年7月18日に執り行われたライプツィヒの郵便局長夫人ヨハン・マリア・ケース(旧姓ラッポルト)の埋葬式のために書かれたという説もあるが、確証はない。オリジナルな資料は失われており、1735年頃に書かれたと思われる筆写総譜が最も古い。したがって、成立はそれ以前であることは確かである。シンメトリカルな構想を持つ全11曲の中心をなす第6曲には5声のフーガが置かれている。
「イエスよ、わたしの喜び」と歌うコラールの第1節は長大なモテットの標題をなす。イエスとともに生きるものは「罪に定められることはありません」と歌う第2曲の強い表出は、「いかなる(罪に定められることは)ない」を意味する“nichts”の反復による圧倒的な効果がもたらすものだ。「肉に従って進むのではなく」の「進む」を意味する“wandeln”に与えられた長い音型による強調も効果的だ。
同じコラールでも、第3曲「あなたの加護のもと」では「サタン」「敵」「雷」「稲妻」といった言葉にふさわしい音型による修飾がみごとである。「霊の法則」を歌う第4曲はソプラノ2声とアルトによる3声によって「霊」のイメージが巧みに描かれている。「竜よ、死の淵よ、恐怖よ」と叫ぶコラールの第3節を歌う第5曲に続いて、「肉ではなく霊の支配下に」と歌う第6曲の二重フーガは、すでに述べたように全曲の中核にあたり、モテットの中心的な精神が述べられる。
第7曲のコラール(第4節)は「すべての財宝よ、去れ」とキリスト者の決意が表明されるが、ここでも「苦しみ」「艱難」「十字架」等のイメージが<ため息>の音型によって描かれる。
「霊は義によって命となる」と歌う第8曲は、第4曲とシンメトリーをなす3声曲だが、ここではアルト、テノール、バスの3声部による。「罪によって死んでいる体」と「義によって命となる<霊>」という相反するイメージの対照がみごとに表現されている。続く第9曲は4声だが、通奏低音とバスを欠いた上4声によって、この世からあの世への移行が美しく表現される。「自堕落な生活」という語をめぐるフガートがアクセントをなす。歌詞はコラールの第5節だが、コラール旋律はアルトによって定旋律として示される。
第10曲の音楽は第2曲のそれと共通であり、第11曲のコラール(第6節)も第1曲と同じだから、全体のシンメトリーは鮮明に示され、どんな苦しみにあっても「イエスよ、あなたはわたしの喜びであってください」と歌いながら、壮大なモテットが完結する。
***アンサンブルクライス第1回演奏会プログラムより
(1995年9月15日川口リリア音楽ホール)

モーツァルト『Der Messias メサイア』KV572
序言
モーツァルトによるヘンデル作品の編曲は、特に興味深いものである。これらの曲はヘンデルの作品中もっとも完成度の高いものとされ、その編曲はモーツァルトの創作活動における最後の時期にあたるからである。
モーツァルトがヘンデルのオラトリオを編曲したのは、すべてゴットフリート・ヴァン・スヴィーテン男爵の依頼があったからである。モーツァルトはすでに子どもの頃に、ウィーンでヴァン・スヴィーテンと知り合っている。ウィーンに居を移してから、モーツァルトはたびたび日曜音楽会(マチネ)に通い、ヴァン・スヴィーテンの豊富な蔵書、なかでもバッハとヘンデルの作品から、自らの芸術のために有効な刺激を受けとった。
1780年代のはじめ、ヴァン・スヴィーテンとウィーンの貴族仲間が集まって、音楽愛好会を作った。個人宅で招待客のために開かれるその集いで、毎年 ― 1787年以降は好んでモーツァルトの指揮で ― 四旬節やクリスマスの時期にハッセ、C. Ph. E. バッハ、そしてとりわけヘンデルのオラトリオが演奏された。モーツァルトによる編曲も、これらの演奏会のために作られたものだった。1788年11月、モーツァルトはヘンデルの「アシスとガラテア」を編曲した。メサイアの編曲は1789年2月から3月初めに行われた。「聖ツェツィーリアの讃歌」および「アレクサンダーの饗宴」の編曲は、1790年7月であった。
メサイア編曲の初演は、1789年3月6日、ヨハン・エステルハージ伯爵の家で行われた。その後もスヴィーテン男爵の周辺で ― 1789年4月7日にはふたたびエステルハージ伯爵家、1795年4月5日にはヨハン・ヴェンツェル・パール侯爵家、1799年12月23日、24日にはシュヴァルツェンベルク侯爵の冬の離宮で ― 演奏されたことが、カール・ツィンツェンドルフ伯爵の日記から分かっている。
バロック音楽では、オラトリオは ― この点、オペラと似ているが ― 演奏のために編曲されるのが慣例だった。モーツァルトの編曲も、この伝統にしたがっている。まず独唱部分が変更されねばならなかった。すなわち、楽章ごと移調する、短縮する、新しい楽章を補うなどである。楽器編成はオーケストラの質に合わせて決められた。音楽的な規則にある程度のっとっていれば、指揮者は自由にいずれかの声部を別の楽器で補強してよかった。したがって、ヘンデルのオラトリオを演奏せよとのヴァン・スヴィーテンの依頼には、したがって、この作品を適切に編曲せよとの要請も含まれていたことになる。創造(作曲)と再現(演奏)の能力は当時、別々の音楽家の表現形態とは見なされていなかった。むしろ芸術家は古くからの習わしにしたがって、作曲家としても、演奏家としても同じくらいすぐれていなければならなかった。
ヘンデル作品の合唱部分の編曲には、バロック期のインストゥルメンテーションの特徴が見られる。モーツァルトは、当時の言い方によれば、「ハーモニーに乗せ」ている。ホルンとトランペットの豊かな音に木管楽器が加わり、これらがたいていユニゾンで合唱の上声部に随伴する。これはバロックの「合唱斉唱」(Chori pro cappella)、すなわちリピエニストも共に歌う、全員斉唱の編成を思い起こさせる。オルガンの響きに匹敵する効果を得るために、こうした斉唱部分はユニゾンで補強するのが通例だった。この伝統から、モーツァルトによるメサイア編曲において、トロンボーン・パートが斉唱のアルト、テノール、バスにつねに付き従っていることも説明しうる。
モーツァルトは演奏上の都合を考慮して、ヘンデルのメサイアの総譜を一部省略する気になったのかもしれない。削られたのは、合唱「永遠の息子をほめたたえよ」、アリア「汝は高みにのぼりて」、およびアリア「ラッパは高らかにひびく」の途中部分である。アリア「神われらの味方なれば」をモーツァルトはレチタティーヴォに変えている。同時代の他の作曲家の編曲とくらべると、この程度の短縮は取るに足りないものである。モーツァルトが行ったこれらのわずかな省略のおかげで、曲全体が引き締まり、密度の濃いものになっているにもかかわらず、初版が出た際には猛烈な批判を浴びた。しかしながら、モーツァルトの編曲は特定の演奏の事情に合わせてなされたものであり、もともと印刷用ではなかったことを忘れてはならない。それはさておき、今日の視点からすると、まさしくこうした側面こそ、時代の変化の中で演奏の実際を示すものとして興味深い。
しかしモーツァルトは、実際の演奏でとうに「即興で」許されていたものをただ単に書き留めたり、または省略したりしたわけではない。フルート、クラリネット、オーボエはアリアの中で、全体の雰囲気の解釈者として登場する。ファゴットはしばしば本来の通奏低音の機能から解放されている。ヴァイオリンには新たなオブリガートのパートが与えられている。(第3部36番二重唱「おお、死よ」)。モーツァルトはとくアリアの音楽の流れを保とうと腐心している。バロック期の慣習として、ヘンデルの時代には、アリアのカデンツでは、独唱歌手が即興で技巧を披露するのをさまたげないよう、楽器は沈黙しなければならなかった。モーツァルトはこの点を変更した。伴奏パートを補い、カデンツに楽器を盛り込んでいった。(たとえば、第2部19番のアリア「なにゆえに争い」T.67等)
この時代の美学的要求は、自然の模倣ということである。聖書の言葉の選び方と、ヘンデルの曲の構想について、後の時代の私たちが説明をとってつけることは慎むべきだが、いくつかの兆しはある。10年後にハイドンが「天地創造」と「四季」を作曲した際と同じように、ヴァン・スヴィーテンがモーツァルトに、歌詞解釈のための方向性をあたえた可能性もある。
演奏の伝統と新たな時代の趣味、因習と流行が、モーツァルトの編曲を決定づけている。しかし、その完全な全体像をつかむには、モーツァルトがヘンデル作品の本来の音形(Klanggestalt)を変えるにいたった、いくつかの外的な要因をも考慮に入れなければなるまい。たとえば、トランペット・パートの変更がそうである。社会的な階層秩序の崩壊は、すでに特権的な管楽器奏者のツンフトの没落をもたらしていた。それがおそらく、クラリーノ(高音トランペット)という管楽器の演奏技巧が忘れ去られ、ヘンデルのトランペット・パートがモーツァルトの時代には演奏不可能とされた原因である。
調和のとれた古典的オーケストラに組み込まれたトランペットは、もはやかつてのように現世での地位や神の全能を表すシンボルとしての、輝かしい楽器ではなくなった。トランペットにあたえられた役割はいまや、オーケストラのひびきをハーモニー的、リズム的に支えること、しかも主として自然音(Naturton)の三和音でであった。バロック期の昔ながらのクラリーノの音色を保つために、モーツァルトは合唱部分ではヘンデル作品におけるトランペット・パートをおさえたり、時には軽やかな木管楽器で代用したりしなければならなかった。アリア「ラッパは高らかにひびく」の独奏パートを、モーツァルトは二度書き直し、最終的にホルンに決めた。当時、ホルンという楽器の演奏技巧の水準は、トランペットとは対照的に、かなり高いものだった。
ヘンデル作品中のオルガン・パートをそのまま残すことができなかったのも、外的な要因によるものだ。モーツァルトの編曲は、個人的な演奏会のためになされたものだったが、ウィーンの貴族の館にはふつうオルガンはなかったからである。
モーツァルトの時代には、チェンバロは独奏楽器であった。しかし、ここではチェンバロはレチタティーヴォの伴奏と、ヘンデルの通奏低音が編曲の中に取り入れられたいくつかの箇所でのみ使われたようである。
バーデン・バーデン、1999年7月
アンドレーアス・ホルシュナイダー
(翻訳 細井直子)

クリスマス・オラトリオ「序言」
バッハのクリスマス・オラトリオがわれわれの音楽界において高い評価を得ている理由、トーマス教会カントールである彼のクリスマス・カンタータの中でも、この作品が特別な位置を占める理由は、主としてその内容がクリスマスの出来事そのものにしぼられていることによる。作品の歌詞の柱は、イエスの誕生、天使によるお告げ、羊飼いたちの礼拝、命名、そして東方三博士についての聖書の叙述である。バッハは個々の祝日のために定められた福音書の章句におおよそしたがっているが、物語の筋の一貫性を保つべきところでは、しばしば教会の規定から外れている。その結果、このクリスマス・オラトリオの六つの部分は、クリスマス期間内の6祝日に分けて演奏されるものであるにもかかわらず、内容的に一つの統一体を構成している。
1729年以降、とくに1733年から1734年にかけての時期、バッハの作曲活動の重点は世俗音楽の分野におかれていた。ライプツィヒ時代の初期が教会カンタータの基礎を築くことにあてられ、その後彼は必要に応じてそこに立ち返ることができたとすれば、1729年以降はテレマンが創設した学生楽団コレギウム・ムジクムの忠実な弟子たちとともに、教会の外でもみごとな編成で演奏を行なうことができた。とくに1733年のアウグストⅢ世の王位継承後、バッハは自らの芸術を示し、また先に「ミサ曲」とともに提出した宮廷作曲家の称号を求める嘆願書の正当性をアピールするために、多数のすぐれた表敬カンタータをザクセン選定候の一族のために演奏している。しかしながら、こうした経緯から、彼の宗教曲と世俗曲との間に矛盾や葛藤を読み取ろうとするのははなはだ見当違いである。それをもっとも明らかに示すのは、これらの表敬カンタータのうち最上の作品が、1734年に成立したこのクリスマス・オラトリオの中に取り入れられていることである。バッハが「われら心を配り、見守らん」(“Last uns sorgen, last uns wachen”)<「岐路に立つヘラクレス」(“Herkules auf dem Scheidewege”)、BWV213>と「鳴れよ太鼓、響けよトランペット」(“Tonet ihr Pauken, erschallet, Trompeten”)の二つの世俗カンタータを、ほぼそのままの形であえてクリスマス・オラトリオの中に取り入れたということは、彼は既に作曲の時点で、一日の生命しかない祝い歌の中から出来のいい作品を救いあげ、教会暦との関係で毎年使われる作品にすることを念頭においていたとも考えられる。
1734年頃、バッハは教会暦の主要な祝祭のために、カンタータのように日曜礼拝の際に演奏するオラトリオを書こうと計画する。現存するのは、クリスマス・オラトリオ、昇天祭オラトリオ、および世俗カンタータの改作である点で特殊な位置を占める復活祭オラトリオである。ことによると聖霊降臨祭カンタータも計画されていたのかもしれない。あるいは実際に作曲されたのだが、後に紛失してしまった可能性もある。
クリスマス・オラトリオの歌詞の作者は不明である。世俗歌を書き換える手なれたやり方は(それがバッハとの綿密な相談の下になされたことは疑いない)ピカンダーを思わせるが、印刷された彼の著作の中にはこの歌詞は見られない。
さまざまな楽章に、当初の構想が作曲の際に変更されたことをうかがわせる箇所が見られる。たとえば第5部第43曲「神よ、御身の栄光を歌い讃えん」(“Ehre sei dir, Gott, gesungen”)の詩節形式は、この詩が本来はカンタータBWV213の中の合唱「民の喜び、汝の喜び」(“Lust der Volker, Lust der Deinen”)に付けられるはずであったことを示している。しかしバッハはこの詩に別の、おそらく新たに作曲した音楽を付けるほうを選んだ。同様のことは第3部第31曲アルトのアリア「わが心にとどめん、この幸いなる奇跡を」(“Schliese, mein Herze, dies selig Wunder”)の場合にも起こったらしく、勘違いでないとすれば、その音楽にはカンタータBWV215の中のアリア「熱意に燃え上がる武器を持ち」(“Durch die vom Eifer entflammeten Waffen”)のものを用いるはずであった。しかしここでもバッハは新しい曲を作り、代わりにカンタータBWV215の音楽は、クリスマス・オラトリオの第5部第47曲のバスのアリア「わが暗き心にも光を与えたまえ」(“Erleucht auch meine finstre Sinnen”)の下敷きとした。ようやく近年になって、福音史家のレチタティーヴォと第59曲コラール「われは御身の飼い葉おけの傍らに立ち」(“Ich steh an deiner Krippen hier”)を除くクリスマス・オラトリオ第6部全体が、バッハの失われた教会カンタータを転用したものであることが証明された。この転用が、今日残されていない本来の歌詞の全面的ないし大幅な書き換えと同時になされたことは疑いない。こうした本来の作曲構想の変更と、それとともに歌詞にも加えられたであろう数々の変更ゆえに、ピカンダーはこの歌詞を自分の名前で発表することを控えたのかもしれない
われわれはこの作品を前にして、さまざまな様式の、ある特定の目的のために作られた古い作品から、内的調和に満ちた新しい音楽を創造するバッハの能力にまたもや驚嘆せざるをえない。バッハの自筆譜(復刻版も出されている)からは、清書と草案とを見比べることで、作曲の過程が手にとるようにわかる。しかしながら、もとの作品を新しい環境になじませる過程は、決してただ表面的に曲の調や編成、各楽章の雰囲気のみを変えることではない。たとえば「幼子のゆりかご」(“Kindelwiegen”)はキリスト教の夕べの祈りの中で何世紀にもわたって受け継がれてきた習慣だが、カンタータBWV213で「快楽」の寓意が若きヘラクレスを魅惑しようとして歌うアリア「眠れ、わが最愛なる人よ、安らかに憩えよ」(“Schliese, mein Liebster, und pflege der Ruh”)が、「眠れ、わが最愛なる人よ、憩いを享受せよ」(“Schliese, mein Liebster, und geniese der Ruh”)という歌詞となってクリスマス・オラトリオの中(第2部第19曲)に取り入れられているのを聞くと、あたかもこのアリアがここでようやくしかるべき場所を得たような印象を受ける。同様のことは、トランペットの象徴にもあてはまる。トランペットはバッハの少し前の時代まで王の楽器とされ、市民生活にはまったく縁遠い存在だった。アリア「王冠と栄光をいただけるご婦人に捧ぐ」(“Kron und Preis gekronter Damen”)では、トランペットはポーランドの女王を称える威厳に満ちたシンボルとして高らかに鳴り響く。それに対して、クリスマス・オラトリオ第1部第8曲バスアリア「大いなる神よ、おお、強大なる王」(“Groser Herr, o starker Konig”)という歌詞のところで、貧しさの中で生まれた幼子イエスのいまだ目に見えざる王国を表わすべきときには、トランペットは神学的な響きを帯びる。クリスマス・オラトリオ第2部で、フルートとオーボエが牧人を表わしていることは誰の目にも明らかだ。結局こうしたことからわかるのは、バッハが世俗曲を型どおりクリスマス・オラトリオに移し変えるだけでは満足しなかったということである。
(アルフレート・デュア Alfred Durr)

モーツァルト『Regina caeli レジナ・チェーリ』(Carus40.049/03)の『序文』の翻訳
1772年7月9日、モーツァルトがザルツブルク宮廷ではじめて正式にコンサートマスターの職を得たとき(それに先立つ数年間、彼はこのポストを名誉職的に務めていたにすぎなかった)、彼は宮廷に期待された職務を果たせないとはまだ予期していなかった。しかし2、3年後には彼はこの仕事を次第に煩わしく思うようになり、とうとう1777年8月に職を辞して、9月23日に母親とともにパリへと出発した。
パリ旅行は21歳の彼に、洗練された世界的大都市の重要な人々と接する機会を与えた。しかしこの旅の間に彼は個人的苦悩にも見舞われた。1778年7月3日、彼の母親が熱病で亡くなったのである。フランスの首都パリでモーツァルトは特に器楽曲を作曲し、一定の職を得たいと望んでいた。不幸なことに、彼のパリ滞在はグリュック信奉者とピッチーニ信奉者との対立が激しくなった時期に重なっていた。彼の企図は頓挫し、9月26日にパリを去った。
1779年1月11日、彼はふたたびザルツブルクに戻った。ここで彼に新たなチャンスが訪れる。レオポルト・モーツァルトが1778年8月31日付の息子宛の手紙に書いているように、ザルツブルク大司教が、宮廷オルガン奏者を兼務するという条件で彼にコンサートマスターの職を提示したのである。モーツァルトはこの申し出を受けた。「レジナ・チェーリ」は彼がザルツブルクに戻ってから数ヶ月の間に作曲されたようである。この聖母マリアを讃える交唱は、復活祭当日の日曜日から聖霊降臨祭8日間の金曜日(第6日)までの間、晩課または終課の最後に歌われるものであったことから、この作品の成立時期をかなり正確に推測することができる。1779年の復活祭日曜日は4月4日、聖霊降臨祭の金曜日は5月28日であった。したがって「レジナ・チェーリ」は、最も早い日程で歌われていたとすれば遅くとも3月には完成していたはずであり、逆にいちばん遅い日程であれば作曲されたのは5月という可能性もある。
1771年と1772年に作曲された「レジナ・チェーリ」K74dおよびK127と比較すると、いくつか相違する点がある。K74dとK127がソプラノ独唱と合唱によって構成されているのに対し、K276はソリストによる四重唱を用いている。ザルツブルクで行われるミサの場合と同じように、ソリストの四重唱はしばしば短いパッセージだけ登場して合唱と対話するようになっている。さらなる相違点は、楽曲の構成である。先に作曲された二作品がいくつかの対照的な楽章からなりたっているのに対し、この「レジナ・チェーリ」には一楽章しかない。その際歌詞は一度ではなく、二度繰り返される。モーツァルトは詩に音楽を付ける際、つねに詩の表現内容に注意を払っていた。特に”Ora pro nobis”という言葉は、これらの作品においてさまざまな音楽的手段によって強調されている。しかしながら、K74dとK127においては”Ora pro nobis”がソプラノ独唱のアリアとされ、前後の楽章とテンポやの表現の点でコントラストをなしているのに対し、K276においてモーツァルトはソリストによる四重唱を投入し、ハーモニーを変え、休符を多用することによって、同様のコントラストを得ている。この休符によって、音楽の流れはそこでいわばいったん停止する。三和音の反復による力強い第一モチーフは、その後に登場してくる、まるで笑い声を思わせるシンコペーションとともに、はじけるような喜ばしさをこの曲に与えている。玉を転がすような合唱のコロラトゥーラもまた、祝典の晴れやかな雰囲気にふさわしい。
ミュンヘン、2000年5月 ベルトルト・オーヴァー Berthold Over
(訳 細井直子)

バッハのモテットについて 樋口隆一
「合唱が数小節歌うやいなやモーツァルトはハッとした。さらに数小節いくと彼は叫んだ。『これは何だ』。そして今や彼の全身全霊は耳となっているようであった。歌が終わると彼は嬉々として叫んだ、『こりゃまさに学ぶべきものだ』。この学校は、かつてセバスティアン・バッハがカントルだったので、彼のモテットの完全なコレクションがあり、一種の聖遺物として保存してある、と説明がなされた。それは正しい、たいしたものだ、と言ったあと、『見せてください』と彼は叫んだ。しかし総譜がなかったので、見事に書かれたパート譜が手渡された。モーツァルトは腰をすえて、パート譜を自分の周囲に、両手、膝の上、手近な椅子の上に散らばらせ、そしてほかの事は全て忘れて、セバスティアン・バッハによって書かれているものの全てに目を通してしまうまで立ち上がらなかった」。
モーツァルトをこれほどまでに魅了したバッハのモテットは、こんにちもなお、わたしたちをも魅了してやまない。